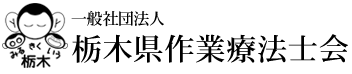一般社団法人えんがお
濱野 将行 氏(代表取締役)
精神科病院、老人保健施設での作業療法士の経験を経て、経営者として高齢者居場所づくり事業年齢・障がいを超えた地域づくりに奮闘する作業療法士濱野将行さんにご活動と思いを聞きました。
作業療法士であり、経営を始めた経緯を教えて下さい。
作業療法士として老人保健施設で働く中で、骨折し短期収集リハビリテーションとして在宅復帰をしても、家で独りという現状が多かったんです。地域につながりがなく、居場所や役割がなく外に出かけずにいると、廃用が進み再度転倒して骨折してリハビリに戻ってはまた地域に帰っていく現状に疑問を持ちました。
家に帰った後に独りでいるという状況を変えることが必要だと思いました。作業療法士として評価・訓練するプロはたくさんいますが、私は家に帰った後に人とのつながりを作る作業療法士を目指そうと思いました。
「誰でも地域の中で役割があって独りぼっちにならない」という私の思う作業療法を実現しようと思ったときに、作業療法士としての加算が無い現実がありました。そのため、経営やソーシャルビジネスを学びました。はじめは高齢者向けの生活支援事業として便利屋を始めました。


生活支援事業からその他事業を広げていった経緯も教えてください。
はじめは、若者たちとはおばあちゃんの家に訪問していました。すると「日中行ける場所が欲しい」「お茶のみできる場所が欲しい」という声が多くありました。目の前で誰から求めていることを大赤字にならない限りやろうというスタンスでだれもが来れる「みんなの家」の経営をはじめました。1Fが地域サロンで2Fが学生の学習スペースになっています。

居場所を作って様々なイベント企画をしてみると、高齢者だけではなく若い学生が来たり、子供連れの親が来たりと多様な人が来てくれるようになりました。こうして、若者が集まってくるようになったので、「みんなの家」を始めた同じスタンスでソーシャルシェアハウスや地域食堂の経営も始めました。

しかし、町を歩いていてもみんなの家にも『障がい』を抱えた人が何故いないのか疑問に思いました。現状を聞き調べていると地域に第三者から生活の支援を受けながら生活をするためのグループホームが少ないことがわかりました。そのため地域交流型のグループホームの経営をはじめました。すると自然に地域に発達障がいや精神障がいのある人たちもいる風景がみられるようになってきました。人の出入りがあるからこそです。


実際にグループホームの経営を始めてどうでしたか?
1手目の経営だと風当りは厳しかったかもしれません。すでに初めから事業を始める時から地域に説明することを心がけておりまして『えんがお』として地域に受け入れてもらえていたので、この時も地域と相談しながら時に協力もしてもらえました。それでも、はじめは地域の人からの目に緊張感がありました。実際に居て触れあってもらうことで少しずつどんな人たちなのか知ってもらえている実感があります。一般的な福祉事業所では利用者が何か地域でトラブルを起こさないようにという意識があると思いますが、私たちは地域で何か起こらないように利用者の管理を強くするのではなく、何か起こった時こそ「なぜそうしたのか」を私たちが地域の人に説明して「社会にはこういう人もいるんだ」と理解してもらうきっかけになると思っています。今までは地域にあまり出てこなかったわけですからはじめは驚いで当たり前だと思います。
社会で障がいを抱えた人と接する経験値が足りないと感じています。
来ている若者たちを見て感じることはありますか?
若者は能力があるのにもともといろいろな事に抑圧されて力を持て余しているなと感じます。えんがおでは、若者のありのままを認めることを大切にしています。すると、それぞれが疑問に思ったことを自分たちで考えてアクションを起こしてくれています。
高校生など若くして、「えんがお」を通して地域に出て問題意識を持ち、医療福祉を志す若者も出てきていて頼もしく感じます。
最後に臨床で悩む作業療法士にメッセージをお願いします。
今は、社会問題が多様化し過ぎていて目の前の人を大切にしようと思ったときに、他職種連携が進んでいますが作業療法士のでであることだけでは対応ができなくなってきています。作業療法士しての知恵は1つの武器として持ち、その他にもたくさん武器があった方がいいと思っています。
使える武器が作業療法だけに縛られてしまうと、作業療法士としての問題意識と業務が乖離して仕事が楽しくなくなってしまうのではないでしょうか。もしそう感じていたら、作業療法士であることを活かして自分も幸せにできる、一緒に「この仕事をしててよかった」と言い切れる作業療法士を模索していきましょう。
疑問を持ちモヤモヤできるのも才能です。一歩地域に出てみましょう。
是非HPかSNSで連絡をとって見学に来てください。最近は内閣府や県外からの視察もあります。
最後に、私たちが目指す構想はこちらです。